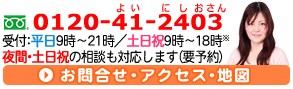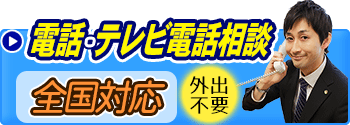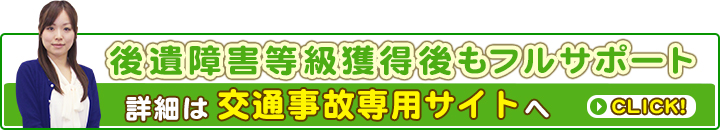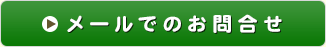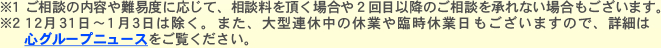後遺障害の申請と症状固定について
1 症状固定になることで後遺障害申請ができる
症状固定とは、傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときをいうものとされています。
症状固定の判断は、基本的には、医師が行い、症状固定に至ると、医師が後遺障害診断書を作成することができます。
2 早期の症状固定に注意
保険会社からは早期に後遺障害申請の案内をされることがあります。
たとえば、保険会社の担当者から「事故から3か月程度経過し、症状が治っていない場合には、後遺障害の申請も考えられると思いますので、後遺障害診断書をご自宅にお送りしますね」などと案内されることがあります。
しかし、症状の内容などにもよりますが、事故から3か月程度では、将来治らないとは言い切れないことを理由に、後遺障害が認定されないことが一般的です。
それだけでなく、症状固定後の治療費は、基本的には賠償対象にならないことから、早期に症状固定となってしまうと、本来は支払われたはずの治療費が支払われなくなってしまうため、要注意です。
3 保険会社から後遺障害申請の案内がされた場合には
損害保険料率算出機構による後遺障害認定は、独自の認定基準があり、かつ、書面審査が中心であるため、提出書類の内容が基準と少し異なるだけで、非該当になってしまうこともあります。
たとえば、痛み(疼痛)について、後遺障害が認定されるためには、基本的には、常時痛であることが必要になりますが、「疲れたときに痛みが生じる」や「長く歩くと痛みが生じる」などと記載されてしまうと、基本的には、非常時痛として後遺障害が認定されないことになります。
保険会社から後遺障害申請の案内があった場合には、そもそも、現段階で後遺障害診断書の作成を依頼すべきか、後遺障害診断を受ける前の注意点としてどのようなものがあるか、などについて、弁護士からアドバイスを受けることが大切です。